ペットロスケア🐾セラピスト橘りんかの豆知識【25】
- りんか 橘
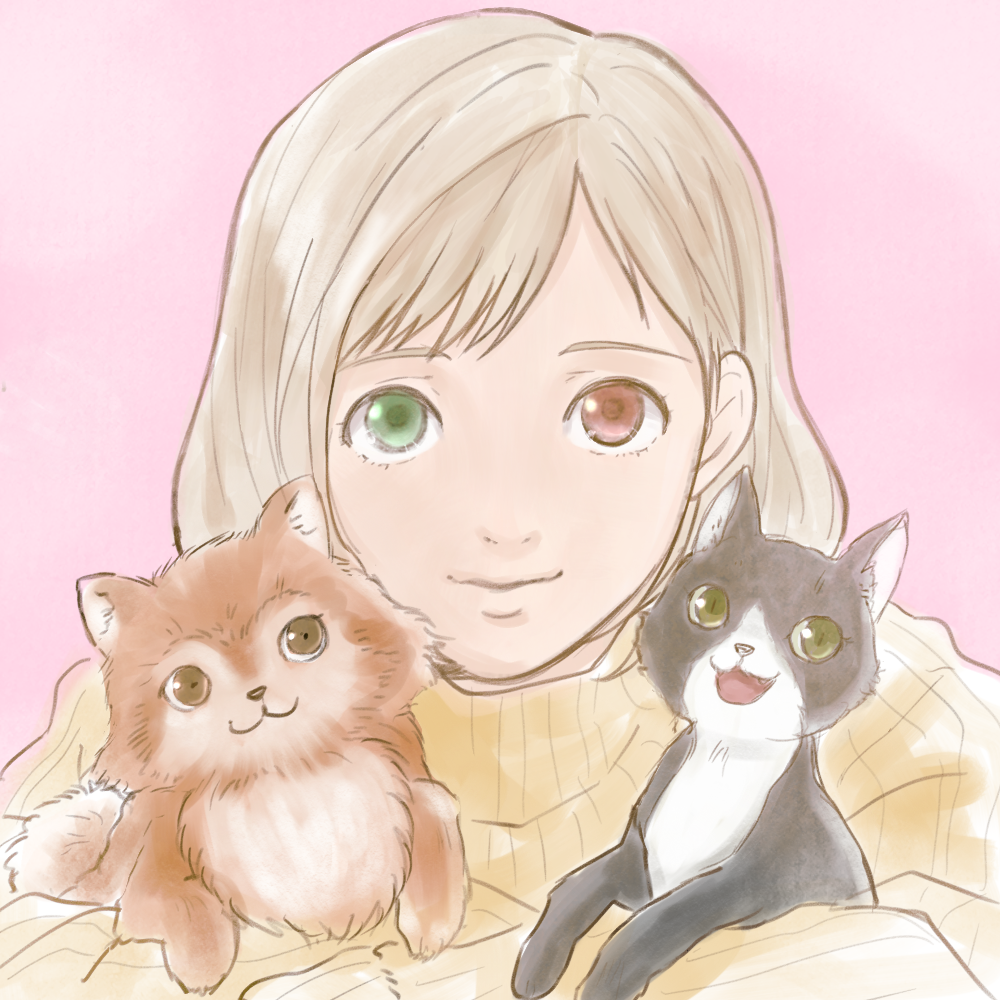
- 2020年5月20日
- 読了時間: 4分
悲しみの5段階
ペットを失った人は、5つの段階を経て徐々に「ペットがいなくなったこと」を受けいれて、ペットロスから回復し、乗り越えられると言います。
今、自分の感情がどの段階にあるのかを、あらかじめ把握しておくことで、ペットロスからの回復・復帰が比較的早くなる可能性があるそうです。
ではその5段階とは何なのか?それは
「否認」「怒り」「取引」「抑うつ」「受容」
の5つのことを言います。
では、1つずつ見ていきましょう。

1:否認 ペットの死を受け入れられない状態
突然のペットの死や、行方不明による別離が信じられず
「そんなことは起こっていない」
と理解を拒絶し、かたくなに受け入れようとしない状態のことを指します。
この「否認」という状態は、人の心があまりの悲しみに「受け入れるキャパシティ」がオーバーした時に、精神的ショックから逃避する自己防衛の本能からくるもので、大なり小なり誰でもこの状態には陥ります。
2:怒り 自分や周囲の、ペットの死に関わった相手を責め、後悔が怒りに変わる
愛するペットを失ったときに
「何もしてやれなかった…」
という後悔の念からくる感情で、自分が愛したペットが死んでしまったのは「誰か」のせいだと思い込み、漠然とした怒りをぶつける段階です。
対象は、飼い主自身だけでなく、ペットの死に関わった獣医師や家族にも向けられます。
死因がはっきりせず「自分が十分にお世話や注意をしてあげなかったからだ」という場合などに強く感じられることが多いです。
3:取引 ペットを失った悲しみの重さを何かに仮託(かこつけること)する
「交渉」とも呼ばれる状態で、飼い主がペットの死によって受けた悲しみから
「ペットの死を覆すことができるのであれば、なんでもする」
と願うあまり、神様といった超常的なものにすがったり
「自分の命と引き換えに、あの子を生き返らせて」
と、現実には不可能なことを願い取引材料にすることが多い。
4:抑うつ 「死」といったネガティブなことばかりを考えてしまう
ペットの死により精神的に深く落ち込み、考えることは常にネガティブな方向へと向かってしまい、何もする気が起きず無気力になる状態を指します。
周囲の心ない言葉などで長引き、こじらせてしまうことで「ペットロス症候群」に陥りやすくなります。
ペットロス症候群になると、心身ともにさまざまな障害をきたす可能性があり、最悪の場合、いなくなったペットの後を追おうとして自殺を図ってしまうことも決して少なくありません。
ただひたすらに気持ちが落ち込む、最も危険な時期です。
5:受容 時が経つにつれ悲しみが薄れ、徐々にペットの死という事実を受け入れる
最後の段階である「受容」とは、「否認」「怒り」「取引」「抑うつ」といった悲しみのプロセスを経験し、ペットを失った悲しみや後悔の念といった感情が徐々に薄れ、ペットが自分の傍らからいなくなったことを受け入れる状態を指します。
人によって時期はまちまちですが、この「受容」の段階に入ることで初めて、ペットを失った飼い主は心身ともにポジティブな状態へと回復していくのです。
「もうあの子はラクになったのだから」
「今頃はむこうで楽しく暮らしているかしら?」
などと、死を前向きに捉えることができるようになり、徐々にかつての日常のペースを取り戻していきます。
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
各段階は、順番に通過するのではなく、前後することが多いです。
特にどの時期が長いか?ということも個人差があり、すぐに受容までたどり着ける人もいれば、いつまでも否認で止まっている人もいます。
ひとつの基準としては、
「1ヶ月」
です。
この1ヶ月が過ぎてもなお、受容までたどり着けいていない場合は、ペットロスである可能性が高いでしょう。
放置してペットロス症候群に陥ることがないように、早めに専門家(カウンセラー・セラピストなど)に相談することをオススメします。
「自分は大丈夫」
「このくらい大したことはないだろう」
「ペットロスとは違うでしょ」
などと甘く見ないでください。
そうしている間にどんどん精神はむしばまれ、ある日突然「死」を選択してしまう、ということもあり得るのです。
強がったりせず、隠したりせず、手遅れになる前に必ずプロを頼ってください。
|д゚){ちなみに、わたしもセラピストですよ~、プロですよ~(笑)




コメント